今回の記事では私が思う、親の立場で最も気にしなければならないことである、心理的安全性について書いていきます。心理的安全性については過去の記事でも少し触れましたので、そちらもご参考になれば幸いです。
心理的安全性とは、子供だけではなく、大人の生活でも同じくらいに重要なものであると考えます。そして、子供はストレス耐性に未熟なことが多いので、特に周りの大人は積極的に心理的安全性を感じさせるようにしなければ、子供が安心して生活するということや、安心して自分のやることに取り組んでいくということは困難になるものと思われます。「子供はストレス耐性に未熟なことが多い」と書きましたが、私も含め大人も多くの場合それほど大差ないと思っています。嫌なストレスを抱えている状態では、仕事も人間関係もうまくいかないことが多くなりますよね。
なぜ心理的安全性が重要と考えているかというと、特に子供が自律的、自主的に勉強に打ち込むようになるにはそれが欠かせないと思われるからです(自律性、自主性の具体的な内容はこちらに書いています)。効率よく学習を進めていくには、誰かに言われてやるのではなく、自分で主体的に、工夫をしながら取り組むのがベストと考えています。その過程としては、子供が自分の考えを言い表し、関係者(志望校や塾の先生、親など)の意見を聞きながら、取り組みに集中、カイゼンをするということになると思います。
心理的安全性が保たれている状態とは、例えば、子供が学習などに取り組む過程で失敗した場合や、うまくいかなかったときに、子供は怒られず、失敗の種類にもよると思いますが、歓迎されるような状態が挙げられると思います。最初からなんでもうまくいくわけはなく、何度か失敗して少しずつできるようになるというのが当たり前のことと思われます。失敗をしたということは、今できないこと、これからできるようになることを見つけられたということで、とてもプラスな情報を得られたということと思われます。目標達成のために漠然とした問題があるとして、具体的な課題を見つけることができたら、それに一つずつ対応することで、確実に問題をなくしていくことにつなげられると思います。
しかし、同じ失敗を何度も繰り返すようなときなど、怒りたくなるという気持ちもあると思います。また、怒らなくては子供がぬるま湯に浸かっているような状態になってしまうのでは?という懸念もあるかと思われます。これについては、今のところ私は基本的には、怒るというのは必要最低限にとどめるようにしています(実際には、なかなか難しいこともありますが・・・)。結果だけを見て後で褒めたり、怒ったりするのではなく、上手くいっていないような感じがしたら、なるべく様子を伺い場合によっては都度都度声掛けをしたり、口出ししたいのを我慢して終わった後にどうだったかを話したりするようにしています。
例えば、都度都度声掛けするのは漢字の書き方を間違えているというような、すぐに直したほうが良いものについてです。これは子供の反感を買うことがあるのでさらにフォローが必要になることがあります(ご参考)。それ以外の、例えば計算問題など、やり方がわかっているようなものについては、時間が終わった後に話し合いをするようにしています。後者の際に気を付けなくてはならないのは、親からの一方的なコメントや押し付けにするのではなく、まずは子供の意見を聞いて、どうしたらもっとやりやすくなるかを一緒に考えるようにしています。最後には、子供ときちんと合意するというのが重要と思われます。
基本的には避けるべきことと思いますが、どうしても怒らなければならないということがあるかもしれません(例えば、故意に人を傷つける、物を壊すなど)。このような時にも絶対に避けるべきなのは、大声で怒鳴るや暴力的な行為をするということと思われます。スクラムはチームの信頼がなければ成り立たない活動です。怒っている場合にも子供に対して感情を爆発させるのではなく、静かに「怒っている」ということを伝え、場合によってはその日の取り組みを途中で終了させるなどでもよいと思います。しかし、その後必ずフォローはするようにしてください。

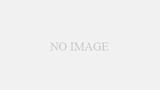
コメント